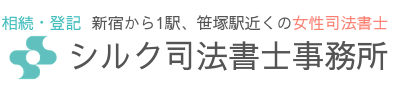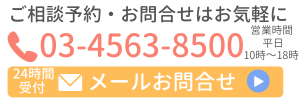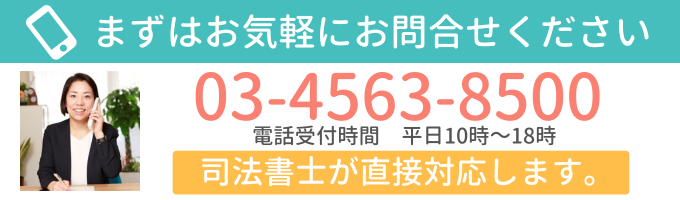父は軽度の認知症ですが、最近になり遺言を残しておきたいと言うようになりました。認知症でも法的に有効な遺言を作成することはできますか?
認知症の場合「遺言能力」があるか判断することは極めて難しい
遺言作成には遺言能力が必要となります。遺言は法律では15歳から作成可能とされています。
遺言能力とは自身の相続関係について理解したうえで、遺言内容を検討して、作成する能力です。この遺言能力に明確な定義はなく、司法書士や弁護士、公証人、そして医師でも判断が難しいのが実情です。遺言書の無効が裁判で争われたときは、遺言を残したときの判断能力や理解力の程度、遺言の内容(シンプルな内容か複雑な内容か)、相続人や受遺者との関係により、遺言能力の有無が判断されることになります。
どうしてもという場合は公証役場と相談して公正証書遺言を検討する
認知症になったからといって、ただちに遺言能力がないわけではありません。しかしながら公正証書遺言を残したからといって、その遺言が有効となるとは限りません。公正証書遺言であっても、相続発生後に訴えにより無効となることがあります。
認知症がまだ軽度であり、どうしても遺言を作成したいという場合は、一人で完結してしまう自筆証書遺言より、第三者が関与する公正証書遺言のほうがよいでしょう。長谷川式簡易評価知能スケールや医師の診断書・意見書などを提出して、公証人から作成の了承を得たうえで、さらに遺言作成の様子をビデオカメラ撮影残すというような慎重な対応が求められます。
成年後見人が選任されている場合は条件が厳しい
なお裁判所から成年後見人が選任されており、成年被後見人となっている方は作成がさらに難しいです。なぜならば、成年被後見人の遺言の作成には民法で「事理を弁識する能力を一時回復した時」に「医師二人以上の立会い」が必要、という2つの厳しい条件が付されているからです。
このように認知症となった後に、遺言書を作成することは難しいです。高齢化社会の現代において、自身の相続で家族や親族が困らないために、遺言は元気なうちに残さなくてはなりません。
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日