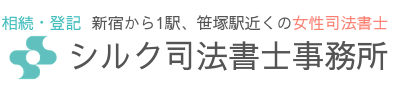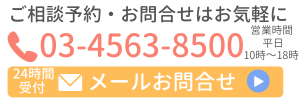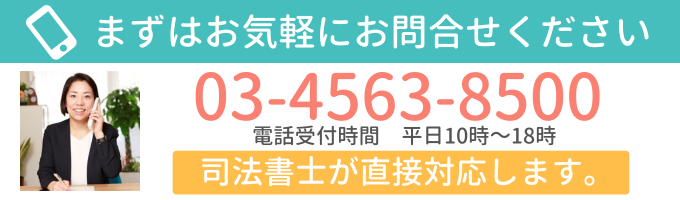遺言作成を通して、もしもの時に備え、自分の意思を明確にしておくことで、家族の負担や争いを防ぎ、安心を届けることができます。また、財産の整理だけでなく、感謝や想いを形に残すことで、人生の節目を穏やかに迎える準備にもなります。
遺言作成を通して、もしもの時に備え、自分の意思を明確にしておくことで、家族の負担や争いを防ぎ、安心を届けることができます。また、財産の整理だけでなく、感謝や想いを形に残すことで、人生の節目を穏やかに迎える準備にもなります。
遺言は、元気なうちにこそ作成すべきもの。気になったらまずはお気軽に司法書士にご相談ください。
特に遺言書を書くべき人
- 子どもがいないご夫婦
配偶者だけではなく、親や兄弟姉妹にも相続の権利があります - 再婚していて、前の配偶者との子どもがいる人
今の家族と前の子どもの間で、財産の分け方でもめる可能性があります - 内縁・事実婚のパートナーがいる人
遺言がないとパートナーに財産をのこすことができません - 身寄りがいない人(相続人がいない人)
遺言がないと、財産は国に引き取られてしまいます。 - 会社経営者
会社の株式は遺産となります。生前に引き継ぐべき人を決めておきましょう。 - 寄付をしたい人(NPOや学校など)
応援したい活動や団体に寄付したい場合は、遺言を残しましょう。
サービス内容と料金
シルク司法書士事務所では、ご事情やご状況にあわせて3つのプランを用意しております。どのプランか迷う場合は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
公正証書遺言作成サポートプラン 報酬10万円(税抜)~
公証人が作成して証人2名の前で読み上げる、証拠力の高い遺言です。高齢の方やトラブルの予見がある方は必ず公正証書で作成しましょう。 詳しくはこちら
自筆証書遺言作成サポートプラン 報酬6万円(税抜)~
「手書き」の遺言は、法務局の保管制度を利用できます。ライフスタイルや家族の変化にともない遺言内容を変更する可能性がある、現役世代の方におすすめです。 詳しくはこちら
シンプル遺言作成サポートプラン 報酬3万円(税抜)
「すべての財産を〇〇に相続させる」と、配偶者や子など1人に相続させる遺言を、手早くに作成したい方のためにご用意しました。 詳しくはこちら
遺言作成を司法書士に頼むメリット
相続を熟考した遺言書ができる
 相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがよいか」「遺言以外に検討することはないか」「遺留分についての対策」「遺言執行者はどうするか」等、課題解決の方法をしっかりと検討することができます。
相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがよいか」「遺言以外に検討することはないか」「遺留分についての対策」「遺言執行者はどうするか」等、課題解決の方法をしっかりと検討することができます。
公正証書遺言は公証役場へ直接依頼することも可能ですが、公証役場では遺言者の遺言内容を公正証書化することが職務であり、個々のご事情をふまえた、相続に関するきめ細やかなアドバイスに応じてくれるとは限りません。また公証人は法律のプロではありますが、相続手続きのプロではありません。
遺言は「実現される」ことがとても大切です。相続手続きの実務に精通した司法書士がかかわることで、「実現される」遺言により近づくことになります。
相続発生後、速やかに遺言執行を進められる
 遺言作成を司法書士にご依頼いただき、遺言書とあわせて担当した司法書士の連絡先を保管いただくことで、相続人は速やかに、相続発生後に相続登記や銀行の手続きなどを専門家に相談や依頼することができます。
遺言作成を司法書士にご依頼いただき、遺言書とあわせて担当した司法書士の連絡先を保管いただくことで、相続人は速やかに、相続発生後に相続登記や銀行の手続きなどを専門家に相談や依頼することができます。
そして依頼する司法書士は「若くて経験豊富な地元の司法書士」であることが重要です。遺言者の相続発生前に司法書士に相続が発生してしまっては、相続人が困ってしまうからです。
司法書士を遺言執行者に指定したり、遺言執行者の復代理人とすることができる
遺言執行者とは、相続発生後に遺言を実行する人のことです。
預金や不動産が複数ある、第三者への遺贈や寄付がある、不動産を売却する必要がある等、相続手続きが煩雑となることが想定される場合は、司法書士など第三者の専門家を遺言執行者したほうが残された相続人の負担が少なくなります。
また、平成30年の民法改正により、遺言執行者には相続人全員への「遺言内容の通知」「財産目録の交付」が義務付けられました。
平易な内容の遺言においては、遺言執行者は、遺産を承継する相続人が指定されることが多いです。しかしながら相続人多数の場合や、関係の悪い相続人がいる場合は、上記の義務を遂行するハードルが高いものとなります。遺言執行を負担に感じる場合は、司法書士を遺言執行者の代理人とすることで、相続登記や銀行の手続きのみならず、遺言内容の通知や財産目録の作成までもおまかせすることができます。
※司法書士が遺言執行者または復代理人となる場合は、相続発生後に司法書士への別途報酬(難易度、遺産額に応じて遺産の1%~3%前後)の支払が必要となります。
公正証書遺言作成サポートプラン 報酬10万円(税抜)~
サポート内容
- 遺言作成や相続に関するご相談
- 戸籍謄本や登記情報など必要書類の取得
- 遺言書の原案作成
- 公証役場との調整
- 司法書士による証人立会(1人分)
※証人2人のうち1人は公証役場で手配します。
※司法書士が遺言執行者になる場合は、証人となることができません。
下記の場合は、文字数や難易度に応じて加算料金が発生します。
- 財産を譲る相続人や遺贈者が3名以上である場合
- 対象となる預貯金や株式が5件以上、不動産が3カ所以上ある場合
- 親族以外の第三者や法人への遺贈や寄付がある場合
- 生命保険の受取人の変更、未成年後見人の指定、認知など、相続・遺贈以外の特別な遺言事項がある場合
報酬以外にかかる実費
- 公証人へ支払う手数料 公証人の手数料(日本公証人連合会のwebサイトへ)
- 公証役場で手配する証人への手数料(1名につき5000円前後)
- (不動産がある場合)インターネット登記情報代(1通332円)
- (司法書士に依頼する場合)戸籍謄本など証明書代
- 郵送通信費、交通費
ご用意頂くもの
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者および遺産を譲る人の戸籍謄本
- 顔写真付き身分証明書
- (第三者への遺贈の場合)遺産を譲る人の住民票
- (不動産)固定資産税の納税通知書 ※価格が記載されている部分
- (預金)口座情報等がわかる通帳
- (有価証券)保有銘柄や数がわかる取引報告書など
自筆証書遺言作成サポートプラン 報酬6万円(税抜)~
サポート内容
- 遺言作成や相続に関するご相談
- 財産目録の作成
- 遺言書の原案(下書き)作成
- 遺言書セット(遺言書記入用紙)のご用意
- 作成した遺言書のチェック
- 法務局の自筆証書遺言保管制度申請書の作成
下記の場合は、文字数や難易度に応じて加算料金が発生します。
- 財産を譲る相続人や遺贈者が3名以上である場合
- 対象となる預貯金や株式が5件以上、不動産が3カ所以上ある場合
- 親族以外の第三者や法人への遺贈や寄付がある場合
- 生命保険の受取人の変更、未成年後見人の指定、認知など、相続・遺贈以外の特別な遺言事項がある場合
報酬以外にかかる実費
- (不動産がある場合)インターネット登記情報代(1通332円)
- (司法書士に依頼する場合)戸籍謄本など証明書代
- 郵送通信費
ご用意頂くもの
- 遺言者および遺産を譲る人の戸籍謄本
- 顔写真付き身分証明書
- (第三者への遺贈の場合)遺産を譲る人の住民票
- (不動産)固定資産税の納税通知書 ※価格が記載されている部分
- (預金)口座情報等がわかる通帳
- (有価証券)保有銘柄や数がわかる取引報告書など
遺言者・受遺者の負担を減らす財産目録を作成します!
2019年の民法改正により、遺言書に添付する財産目録は、すべて手書きではなくではなくパソコン等で印字された書面を利用してよいことになりました。
財産内容を別紙とすることで、遺言者は書く手間をぐっと減らすことができます。
また、財産目録を残しておくことで、相続発生後に、受遺者(相続する人)に遺言執行者がスムーズに迷うことなく手続きを進めることが出来ます。
法務局の保管制度について
自筆証書(手書き)遺言の原本を法務局が預かってくれるため、遺言書の隠蔽・改ざん・紛失のリスクを避けられます。
保管制度を利用した自筆証書遺言については、裁判所での検認手続きが不要となるため手続きをスムーズに進めるk十ができます。
戸籍担当部局と法務局が連携して、遺言者の死亡したら、あらかじめ遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせしてくれる指定者通知制度を利用することができるのも大きなメリットです。
なお、遺言書保管の申出は遺言者本人が法務局へ出向く必要があります。司法書士や親族による代理は認められておりませんのでご注意ください。
-

-
法務局の自筆証書遺言保管制度について
続きを見る
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてはこちらの記事をご参考ください。
-
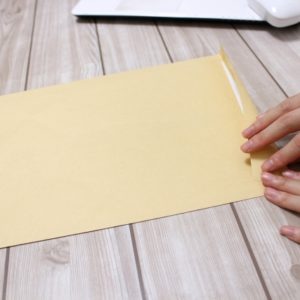
-
自筆証書と公正証書の違い
シンプル遺言作成プラン 報酬3万円(税抜)
サポート内容
思い立ったらスピーディに作成できる!「すべての財産を〇〇に相続させる」と、配偶者や子など特定の相続人1名に相続させる遺言を手軽に作成したい方におすすめのプランです。
事前に戸籍謄本と住民票をメールやLINEで送付頂いた上でご来所頂き、当事務所で自筆証書(手書き)遺言を完成させます。
「配偶者や子に迷惑をかけないために最低限の遺言を残しておきたい」という遺言作成を応援するべく、気軽にご利用いただけるサービス・料金設定にしました。
注意ポイント
- 相続人以外への遺贈は、本プランの対象外です
- 遺言執行者は、財産を承継する相続人とします
- 財産目録の作成や、具体的な預貯金や不動産の記載は行いません
- 予備的遺言は設けません
- 法務局の自筆証書遺言保管制度の利用をご希望の場合は、申請書はご自身で作成下さい
ご用意頂くもの
- 遺言者および遺産を譲る相続人の戸籍謄本
- 遺言者の住民票
- ご実印
- 顔写真付き身分証明書
遺言作成をするなら、プチ遺贈寄付をしてみませんか?

「遺贈」とはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単にいうと、自分の遺産を誰かに贈ることです。遺言書を残すことにより、あなたの遺産の全部または一部を、相続人ではない個人や法人に贈ることができます。この贈る相手が、事業や社会貢献活動を行う法人・団体や、公的機関であれば「遺贈寄付」になります。
高齢化の進む日本。個人が蓄えたお金は、超高齢者から高齢者へ、持つものから持つものへと、循環されていきます。
この1%だけでもよい、日本や世界の問題解決のためにお金をまわすことができれば…未来は少し変わると思いませんか?
日本では寄付というと、大金持ちが行うことというイメージが強いかもしれません。しかしながら、90日間で約5.4万人の支援者から約8.8億円をあつめた国立科学博物館のクラウドファンディングのように、ひとりあたりは少額でも、多くの想いと賛同が集まることにより、大きなお金となり力となります。
寄付先は、あなた次第。課題解決に取り組んでいる法人、お世話になった自治体や教育機関、夢を実現するプロジェクト。
遺贈寄付であれば、死んだ後にお金が残ってなければ寄付をする必要はありません。つまり老後のお金の心配なく、最後に残ったお金で世の中の役に立ち、未来の世界とつながることができるのです。
司法書士長谷川絹子は、遺贈寄付の文化を日本に広める活動を行う日本承継寄付協会の会員であり、承継寄付診断士1級の資格を取得しています。
遺贈寄付について興味を持たれましたら、まずはお気軽にお声がけ下さい。ご来所でご希望の方には、遺贈寄付先の情報冊子「えんギフト」をプレゼントしております。