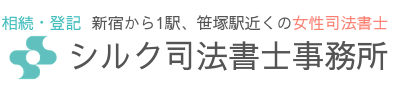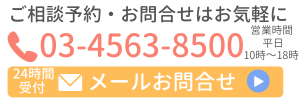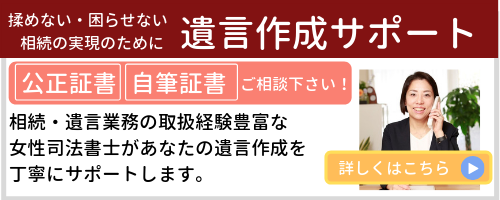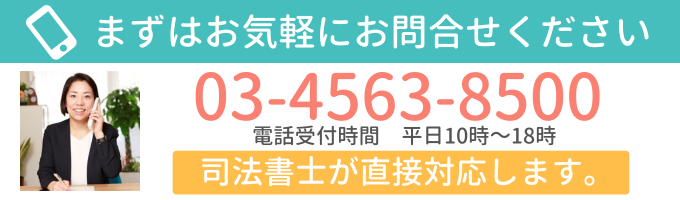金銭にルーズな次男の息子に生前に相続放棄をさせることはできますか?
私には、長女、長女、次男と子が3人います。配偶者である夫は他界しております。私が死んだら、自宅は同居している長男に、その他貯金などは孫のために長女に相続してほしいと考えています。次男はお金にルーズで、金銭トラブルが絶えず、3年前の援助を最後に親子の縁を切っている状態です。次男に遺産がわたるとあっという間に亡くなってしまうことは目にみえています。生前に相続放棄をさせる方法はないでしょうか?

生前に相続放棄をさせる方法はありません。遺言書で対応しましょう
現在の日本の法制度においては、生前に相続放棄をさせる方法はありません。また、実親と実子の親子関係を解消する方法もありません。このようなケースにおいては「遺言書を残す」ということが、現実的な対応となります。しかしながら遺言書を残しても、遺留分は存在します。
遺言書を作成するにあたっては、遺留分に注意を
遺留分とは、財産を一切相続できず生活に困ってしまうようなことなどがないよう、法律で定められた相続人の最低限の権利です。財産を長女と長男に相続させるという遺言を残したとしても 遺留分(法定相続分の 2分の1)については、次男に請求する権利があります。子3人の法定相続分がそれぞれ3分の1とすると、次男は遺産の6分の1については、財産をもらう権利があるのです。
遺留分は、相続人が「請求すること」ではじめて権利となるものです。簡単にいうと、請求されなければ遺留分に対応する必要はないのです。こうしたことから、遺言書の付言に(遺言書本文の最後にそえるメッセージ。法的な効力はありません。)
次男には、こういう理由から遺留分を請求しないでほしい、と残すことも、1つできることではあります。また、相続財産次男の遺留分に相当する金銭をあらかじめ確保しておくことで、残された相続人が遺留分の対応で悩まされないようにすることができます。
生前に相続放棄はせきませんが、遺留分の放棄という制度はあります
実は、この遺留分については生前に裁判所へ放棄の申立をすることができます。しかしながら、あくまで相続人となる方が自分の意思で申立をする必要あるため、あまり現実的な方法ではありません。「まとまったお金を貸す条件として、遺留分の放棄をしてもらった」という事案に出会ったことはありますが、これは極めて珍しいケースでしょう。
相続させたくない相続人がいる場合は、まずは遺留分の対策をした遺言書を作成しましょう。
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日