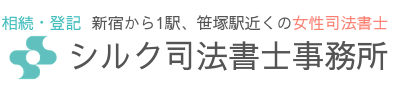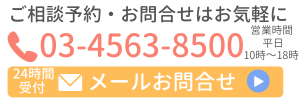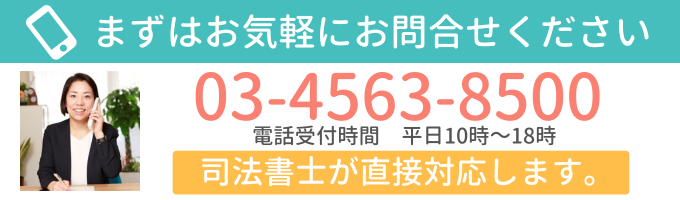相続人は妻である私と前妻との間の息子さんです。私が死ぬまでは夫の自宅に住み続けたいです。
夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、夫の前妻との間の息子さんです。息子さんは前妻のもとで育ったので私とは養子縁組をしていません。遺産は自宅と預貯金がわずかです。自宅を失うと私が暮らす場所がなくなってしまうので、私が死ぬまでは自宅に住みたいですが、私が死んだあとはもともと夫の家なのでいろいろ苦労やご迷惑をかけた息子さんに譲りたいです。息子さんには持ち家もあるため、私の意向に同意してくれているのですが、どのように遺産分割すればよいのでしょうか?
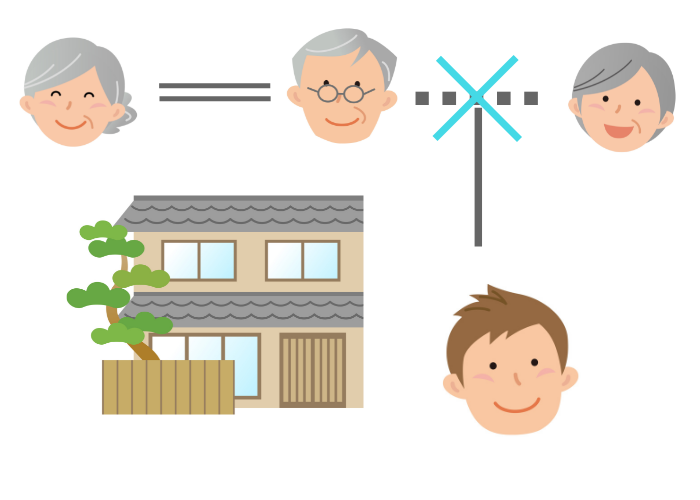
配偶者居住権の設定という方法があります
民法改正により、令和2年より新しく「配偶者居住権」という制度ができました。これは一定の条件を満たせば、所有者である夫または妻が亡き後も、残された配偶者が無償で住む権利を設定できるものです。
今まで、このご相談のようなケースでは以下のような方法が考えられました。
1.息子が自宅を相続して、妻と息子で使用貸借契約(無償で借りる契約)を結ぶ
2.妻が自宅を相続して、妻に自分が亡くなったら息子に遺贈する遺言を残してもらう
しかし、これでは所有権を手にした人が不動産を第三者に売ってしまうことなどもできてしまいます。またいずれか一方が自宅を相続する場合、法定相続分を超える分につき、代償金を支払わなくてはいけません。このため、配偶者が自宅を確保するために夫亡きあとの大切な老後資金である預貯金や現金を失うという問題もありました。このような問題を解決できるのが配偶者居住権です。
配偶者居住権は、高齢化社会の到来にともない、配偶者亡きあとも長きにわたり自宅に住みたいという需要にこたえる制度となっています。また「非嫡出子(婚姻外で産まれた子)と嫡出子の相続割合は同じである」という最高裁判所の判例により民法が改正されたことも導入のきっかけとなったようです。夫が婚姻外でもうけた子に、相続を機に妻が家を追い出されることがないよう、ということでしょう。
配偶者居住権は登記しなくてはいけない
配偶者居住権は、遺産分割または遺言でもってのみ、自宅建物に設定することが出来ます。
居住権を設定できるのは、対象となる自宅建物に住んでいる配偶者のみです。登記をしないと、所有者が第三者に売ってしまった場合などに、第三者に居住権を主張することが出来ません。
今回のご相談のケースにおいて配偶者居住権を設定するためは、自宅の土地と建物については息子さんが所有権を取得して、建物の配偶者居住権は妻が取得するという内容の遺産分割協議書を作成した上で、法務局で登記申請をします。
配偶者居住権が設定されると、制限付きの所有権となるため自由に売買などすることは難しくなります。たとえ、第三者の手に渡ってしまったとしても妻が亡くなるまでまたは設定した期間の到来までは居住権は守られます。
老人ホームに入居する場合は?配偶者居住権を消滅させたい場合
配偶者居住権は、その配偶者が亡くなることまたは設定した期間の到来により消滅します。
では、配偶者が亡くなる前または期間の到来前に、いわゆる老人ホームに入居するため自宅に住む必要が亡くなったという場合はどうするのでしょうか?これは、所有者と居住権者の合意により居住権を消滅させることができます。居住権を消滅させれば、所有者が売却することも可能です。
ただし注意しなくてはいけないのは、配偶者居住権を合意により消滅させると、税法上は「所有者に無償で居住権を贈与した」というみなし贈与となり、贈与税の対象となることです。なお、居住権の消滅させるにあたり、居住権相当の金銭を配偶者にわたす、つまり居住権の買取をすれば贈与税は発生しません。また、所有者の同意を得て賃貸に出すという方法も考えられます。
配偶者居住権の設定は専門家に相談した上で慎重に
配偶者居住権は便利なようで、法律面と税金面を十分に検討しなくてはいけない難しい制度でもあります。
配偶者が終身自宅に住み続ける方法としては、配偶者居住権のほかにも、家族信託の利用や、生前であれば「おしどり贈与」といわれる婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用住宅(またはその資金の)贈与に限り2000万の贈与税控除を認める制度の検討も考えられます。
保有している財産、当事者の将来設計、相続税対策などをふまえて、司法書士や税理士などの専門家に相談の上、慎重に検討することをおすすめします。配偶者居住権を検討しているという方、相続対策として気になっているという方。当事務所では配偶者居住権にも対応した相続登記おまかせプランをご用意しており、不動産と相続に詳しい税理士もご紹介することも可能です。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日