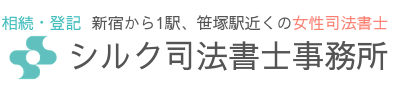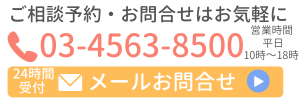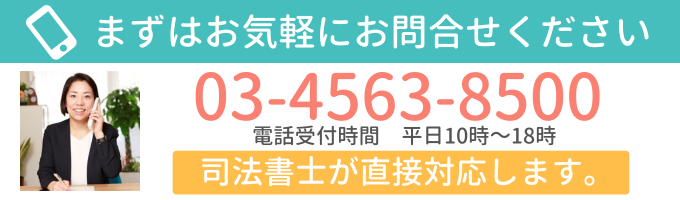グローバル化社会が進んだ昨今、「相続人が海外にいる」ということが決して珍しいことではなくなりました。相続人が海外在住である場合、相続登記や相続手続きはどのような点が異なり、注意しなくてはならないのでしょうか?
ここでは主に、「国籍は日本にあるけれど、海外に住所を移している相続人」がいる場合に必要とされる「署名証明書(サイン証明書)」について解説します。

印鑑証明書のかわりとなる署名証明書(サイン証明書)
相続登記や金融機関の相続手続き等においては、遺産分割協議書や手続き書類に実印での押印を求められますが、その証明として印鑑証明書の提出が求められます。ところが、海外に住所を移してしまった日本人の方は印鑑証明書を取得することができません。そのような方のために現地の領事館で取得できるのが署名証明書(サイン証明書)です。署名証明書(サイン証明書)は日本の印鑑証明書に代わるものとして発行されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の目の前でなされたことを証明するものです。
このような証明書の取得にあたっては、原則は領事館に自ら出向く必要があります。また、当日訪問しても受付してもらえない厳密な予約制となっているところもあるため、まずは事前に管轄をする領事館を確認の上で申請方法について問合せをしましょう。
なお、はるか遠く離れている場合など,領事館のサイン証明書(署名)を得することが困難なときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。
サイン証明書(署名証明書)には形式は2つあるので注意
相続手続きに求められる署名証明書(サイン証明書)には2つ形式があります。形式1は貼付型や合綴型といわれる領事館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した書類(遺産分割協議書など)を綴り合わせて割印を行うもの,形式2は単独型といって印鑑証明書のようにその紙単体で申請者の署名をで証明するものです。
不動産の相続登記においては、多くの法務局においては形式1の貼付型を求めます。一方金融機関の相続手続きは形式2の単独型で足りるとすることが多い印象です。発行手数料は有料ですので提出先は何カ所で、どちらの形式を求めているか、原本は返却してもらえるのか、等を事前に確認した上で必要通数を確定しましょう。
なお、形式1の貼付型の署名証明書(サイン証明書)を取得するためには、綴る書面とパスポートなどの必要書類を持参の上で、現地の領事館に出向き申請します。このため相続人間の話し合いがまとまり、遺産分割協議書が作成されたあとではなければ申請をすることができません。遺産分割協議書と合綴型した証明書は、当然海外から日本へ送ってもらう必要があるため、万が一の郵便事故等に備え、1枚に相続人全員が押印する方式ではなく1人1枚押印する遺産分割協議証明書方式で用意することが好ましいです。
また、不動産の取得者になる場合など、手続きに応じては住民票に代わりとなる「在留証明書」という書類も必要となる場合があります。
相続手続きのために一時帰国できる場合
また、相続手続きのためや何かのついでに一時帰国することが出来るという場合は、下記の選択肢もあります。
1一時帰国をして日本の公証役場で署名証明書(サイン証明書)を取得する
2一時帰国をして日本に住所を戻し、印鑑証明書を取得する
署名証明書(サイン証明書)のデメリットは、記載内容にミスがあったり協議をやり直す場合などで遺産分割協議書を再作成した場合に、提出先が求めているのが形式1の貼付型であると、再度同じ手順を踏まなくてはならないことです。このため、少々面倒ではありますが2を選択される方も少なくはありません。
海外在住の相続人がいる場合は「確認」と「スケジューリング」が肝
サイン証明書を取得する手続き自体は、そこまで難しいものではありません。しかし、多くの方はお仕事などで忙しい生活を送る中、時間をやりくりして領事館に出向き申請を行うことになります。領事館はごく限られた都市にしかありませんので、近くに領事館がないかもしれません。なかなか予約がとれないということもあります。「提出先への確認不足で、もう一度取得をお願いすることに!」となった場合は、果たして笑顔で了承してくれるかどうか難しいところです
海外在住の相続手続きは、海外に住んでいる相続人の仕事や生活の都合、現地の領事館の混雑具合、郵便事情など、スケジュールのコントロールが難しいため、相続税申告やある、不動産の売却を控えているなど期限がある場合は予定をスケジュールに余裕をもって無駄やミスなく進めていかなくてはなりません。
また、遺産分割協議書はできれば1人1枚の遺産分割協議証明書のほうがよい、海外在住の方はアルファベットと日本語(カタカナ)表記を並列したほうがよいなど書類についても気を遣うポイントが多くあります。
このような理由から、相続人や遺産が多くないとしても、海外在住の相続人がいる相続手続きをスムーズに確実に進めるためには、司法書士などの専門家に相談・依頼されることをおすすめします。
、
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日