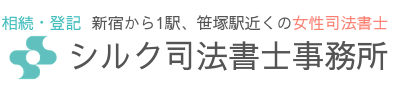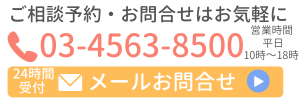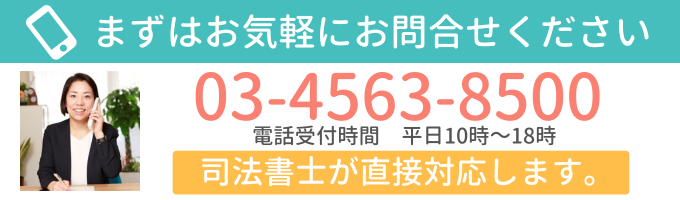遺産分割協議10年後に発覚した半血兄弟
かつて「10年前に相続人全員の遺産分割協議書へのハンコも印鑑証明書も揃えたので、残る登記だけを」という依頼がありました。被相続人(亡くなった方)に配偶者との子はなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人である案件でした。昭和初期の生まれの方なのでご兄弟も多く、亡くなっている方については子(甥姪)が相続人となるため、相続人は総勢8名ほど。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、この相続関係を調べるためには、「兄弟姉妹の全て」つまり両親から生まれた子の存在を確認するため、両親の出生から死亡までをたどる戸籍が必要となります。ところが蓋をあけてみると、「母の婚姻前〜出生の戸籍」の取得がもれており、取得してみたところ、被相続人のお母様には前婚でのお子様がいることがわかりました。
つまり、被相続人やご兄弟からするといわゆる異父兄弟、半血兄弟がいたのです。このことをご親族の皆さんはだれも知りませんでした。
旧民法の家制度における離婚と子の所属
相続業務に携わり戸籍を多く読んでいると、昔(明治〜昭和初期)においても離婚は決して珍しいことではなかったのだということを実感します。家を存続させるためや子を育ててもらうための養子縁組なども頻繁に行われており、現代よりも戸籍の出入りの動きが激しい印象です。
旧民法の家制度においては産まれた子は家長率いる「家」に所属するものであり、夫婦が離婚すると子は妻が連れていくことなく夫の家に残していくというケースが多かったようです。夫婦が離婚をすると妻が親権を持ち、再婚する場合は子連れ再婚となりステップファミリーを形成するという現代の姿とは異なります。
そして旧民法の家制度下において再婚した場合は、前の結婚のこと、つまり前の家のことは子どもたちに話すことなく生涯を終えるという方が少なくなからずいらっしゃったのでしょう。実は我が家も祖母が亡くなってから戸籍を取得して初めて、祖父との結婚は2度目の結婚であったことを知りました。
前婚のことや残してきた子のことを話さないまま亡くなったため、相続のために戸籍を取得して初めて「半血兄弟の存在を知った」というご相談は、相続業務に携わっているとしばしばあります。
うっかりに見逃しがちな母の婚姻から出生をたどる戸籍
兄弟姉妹が相続人となる相続においては、父はしっかり婚姻~出生までたどったものの、うっかり母の婚姻~出生の戸籍をとることを失念してしまうことがあります。特に相続関係が複雑であったり相続人が多いケースでは、数に気をとられて専門家でも見逃しがちなポイントです。冒頭のケースもまさしくこのパターンです。
専門家の場合はセルフチェックで気づきますが、一般の方においては上記の例のように気付くことなく、相続手続きのために銀行や法務局、司法書士などの専門家に戸籍を提出して「母の婚姻前〜出生の戸籍」が足りませんと指摘され、取得してみたところ「母の前婚の子=異父兄弟=新たな相続人」が判明するというケースがあるのです。
もちろん母だけではなく父に前婚の子や、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)がいる場合もあります。こちらは戸籍そのものは取得していても、昔の戸籍は戸籍の文字が読みにくかったり戸籍に入っている人数が多く、見落してしまうことがあります。
兄弟姉妹の相続登記や手続きは、戸籍収集から専門家にご相談・ご依頼を
冒頭の例では、戸籍を辿ったところ半血兄弟にあたる方はすでに亡くなっており、そのお子さんが相続人であることがわかりました。お子さんは1人のみで、戸籍の附票で確認した住所へ事情を説明したお手紙を出したところ、手続きにご協力頂けるとのこと。次は相続人への事情説明です。みなさん10年前に相続は終わっている話だと思っていたので寝耳に水、半血兄弟の存在にも当然ながら驚きです。
さらに10年経過したことで、当時の相続人に相続が発生したため関係者も15人に増えましたがみなさまにご理解頂き、再度、遺産分割協議書と印鑑証明書を整えることができました。
この件は無事解決することができましたが、そうとはいえ、やはり10年前に司法書士などの専門家に戸籍収集から依頼をしていればと・・・思ってしまうところです。専門家にとっては戸籍収集は「相続人を調査する作業」であると捉えている点が、一般の方が戸籍を収集する場合と少し意識が違う点かもしれません。
当事務所では、人数の多い兄弟姉妹の相続案件や、会ったことがない半血兄弟のいる相続案件の取扱件数も豊富ですので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日