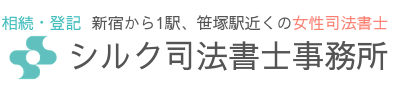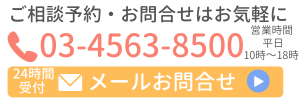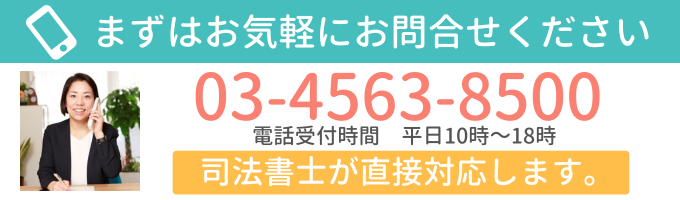亡くなった人に借金がある場合、2つの選択肢があります
- 相続放棄をする
- 借金を相続人が相続して支払う
1の相続放棄を選ぶのは、不動産や預金といったプラスの財産より借金が多い場合です。相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄申述」の手続きをする必要があります。相続放棄をすると家や預貯金といったプラスの財産も相続することができません。
2を選ぶ場合は、借金よりプラスの財産が大きい場合です。借金を相続する場合は、相続人全員で借金を支払うのではなく、プラスの財産と同様に、「A銀行に対する借入金はXが相続する」というように、特定の相続人が相続することもできます。住宅ローンが残っている家の場合は、家を相続する人がローンも相続することになるでしょう。
悩ましいのは、プラスの財産より借金がわずかに多いが、相続放棄をすると家を手放すことになり住むところを失ってしまう、という場合です。この場合は、今後の返済可能額や新たに住む住居の家賃等をふまえて慎重に検討する必要があります。また、「相続した分の金額だけ、借金も相続すればよい」という限定承認を選択するという方法もあります。
相続放棄をすれば借金は払わなくてよい
裁判所へ相続放棄申述の申立をして受理されると、相続人は「相続人ではない」という扱いになるため、亡くなった方の借金は1円も払わなくてよくなります。有名人のエピソードなどで「死んだ親の借金を背負って・・・」というような話もよく耳にするので「相続放棄をすれば借金は払わなくてよい」という事実に驚かれる方もいらっしゃいます。
相続放棄のデメリットは、不動産や預金といったプラスの財産もすべて手放す必要があるということです。また、死亡保険金や遺族年金は受け取れますが、亡くなった本人が受け取るはずであった入院保険などは、受け取ることができません。
相続放棄をするにもかかわらず、相続財産を受け取ったり消費してしまうと相続をした(法律用語では相続の承認をしたといいます)とされ、相続放棄ができないこともあります。
借金を相続する場合、借入先と債務者を変更する契約をむすぶ
借金を相続して、借金を返していくと決めた場合は、借入先との契約変更が必要となります。
相続人同士で遺産分割協議書で「甲銀行の借入金は相続人Aが相続する」と決めただけでは銀行に対する効力はありません。借金を相続すると決めた場合は、借入先に連絡をしてその旨を伝えましょう。債務者を変更する契約書に相続人全員で押印することにより、借金を相続しない相続人は、はじめて借金から解放されることになります。
借金を相続するが支払が苦しいという場合は、任意整理の検討を
相続放棄をすると家を手放さなくてはいけなるので借金を相続することを選んだが、支払を続けていくのはかなり苦しいという場合はどうすればよいのでしょうか?
借入先が利息の高い、いわゆる消費者金融や銀行のカードローン等の場合は、「司法書士や弁護士等の専門家が介入して、残った借金の利息を(原則)カットして、3年~5年の間で分割払いをする」任意整理を検討しましょう。なお、銀行の住宅ローンの場合は、任意整理をすることができません。住宅ローンはもともと金利が低く、支払期間が長いため、支払期間が3年~5年と設定される任意整理をすると逆に月々の支払いが大幅に上がってしまうからです。
借金には過払い金が発生していることも
過払い金とは、過去に、法律で定めれた金利上限より多い割合で金利を支払っていた場合、その払いすぎていた分を貸金業者から返してもらえるお金のことです。亡くなった人に過払い金が発生していた場合は、その相続人が過払い金を受け取る権利があるのです。
亡くなった方が、平成20年より前からいわゆる消費者金融から借金をしており、借りていた(返済をしていた)期間が長い場合は、過払い金が発生している可能性があります。借金があるので相続放棄をしようと思っていたが、司法書士や弁護士に相談したところ過払い金の存在を指摘され、相続放棄をするのをやめたというケースもあります。相続放棄は相続発生を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますし、過払い金は最後に返済をしたときから10年が時効(権利が消滅してしまう)となりますので、気になる場合は、早めに専門家に相談しましょう。
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日