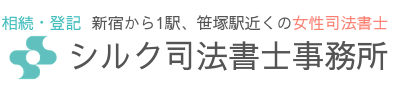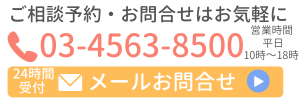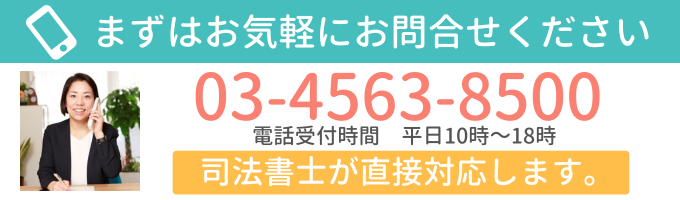相続放棄の3つのルール
相続放棄には決まり事があります。まずは以下の3つは必ず理解してから、相続放棄を検討するようにしましょう。
その1 相続放棄は一度したら取り消すことができない
相続放棄は一度すると、相続関係の確定のため、相続放棄を撤回することはできません。
「そんなに財産があると知っていたら相続放棄をしなかった」といっても取り消すことはできないのです。簡単に取消や撤回ができてしまうと、いつまでも相続関係が安定せず、債権者や利害関係人が困ってしまいます。詐欺や脅迫によって、相続放棄を強いられた場合は取消可能ですが、取消は放棄した時と同じく「相続放棄取り消しの申述」として裁判所へ申立する必要があり、証拠の提出等を求められ、容易に認められるものではありません。
その2 相続放棄をしたらプラスの財産は相続することできない
相続放棄をするということは、相続人ではなくなるということです。相続放棄をすると、借金を支払わなくてよくなりますが、同時に預貯金や不動産など一切の財産を継ぐことができなくなります。「借金だけ相続放棄する方法」や「家だけ残す方法」というものは存在しません。このため、プラスの財産も借金もどちらもある場合は、相続前にしっかりと財産調査をすることが重要となります。
その3 相続放棄をしたら次の世代の相続人に相続権がうつる
配偶者や子が相続放棄をした場合は、亡くなった方の親、亡くなった方の兄弟や甥姪と相続権がうつっていきます。相続権がうつるということは、亡くなった方が残した借金の請求が次の世代の相続人に行く可能性があるということです。この点を知らずに相続放棄を進めてしまうと、後で親族関係にしこりを残すこともありますのでご注意ください。
相続放棄をする理由別 注意するべきポイントとは
相続放棄をする理由によって、「本当に裁判所へ相続放棄申述をしたほうがよいのか?」慎重に検討する必要があります。理由ごとに注意するべきポイントを紹介します。
プラスの財産より借金のほうがはるかに多いから
この理由での相続放棄場合には、迷う必要はほとんどないかと思います。相続財産がプラスかマイナスか、3ヶ月の熟慮期間内に判断がつかない場合は「熟慮期間の伸長」の申立を利用することもできます。
疎遠な親族で面倒にかかわりたくないから
「アパートの大家から片づけに協力してほしいと要請がきた」「市から滞納していた税金の催促がきた」ということから疎遠な親族の死亡を知った場合は、「面倒にはかかわりたくない!」と相続放棄の手続きを早急に進めてしまうものです。また「両親の離婚以来、数十年会っていない父が亡くなった」というようなケースでは、感情的に相続放棄を選択してしまうことも。
しかしながら、相続放棄をした場合は、あとでどんな財産がでてきたとしても相続することはできませんので、できる限りの情報収集した上で決めるようにしましょう。
相続放棄をしたほうがよいと他の相続人にいわれたから
亡くなった方の財産はしっかりと調べましたか?「借金があるから相続放棄したほうがよいといわれたが、実は財産があったので相続放棄を取り消したい」というご相談をしばしばいただきますが、残念ながら「騙された」という証拠がない限りは、裁判所へ相続放棄を取り消すことはできません。相続放棄は、あくまでご自身の判断で、慎重に検討しましょう。
○○に相続させたいから
「家を継ぐ長男がすべて相続する」ので、自分は相続を辞退するというケースで早期に相続放棄申述の手続きをする方がいらっしゃいます。しかしながら、これは予期もしなかった相続人が出てきたときにトラブルになることがあります。
よかれと思って相続放棄をした後、知らなかった異母兄弟などの新たな相続人が発覚してしまうと、自分が相続放棄をしたことにより見知らぬ相続人の相続分が増えてしまうということがあります。○○に相続させたいという場合は、相続放棄申述ではなく遺産分割協議によっても実現は可能ですので、どちらが適しているのかしっかり検討するようにしましょう。
また、「配偶者である母にすべて相続させたいから」という理由で放棄をしても、子が相続放棄すると直系尊属(父母・祖父母)や兄弟姉妹または甥姪に相続権がうつることにより、よりややこしいことになるケースもありますのでご注意ください。
-

-
相続放棄と遺産分割協議どちらを選ぶ?~遺産放棄の方法~
相続放棄申述は、戸籍などの書類がそろえて管轄の家庭裁判所に出向けばその日のうちに手続きすることもあるため、専門家に相談せずに早急にご自身で行われる方もいらっしゃいます。しかしながら、上記のようなことを理解していないまま手続きを進めてしまい、あとで相続放棄を後悔されるという方も少なからずいます。相続放棄の手続き自体はそう難しいものではありませんが、ルールが大変厳しいため、判断には慎重さが求められます。相続放棄を検討する場合は、ぜひ一度専門家にご相談下さい。
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日