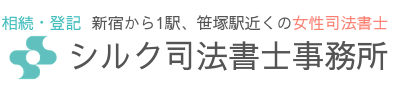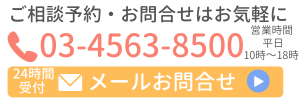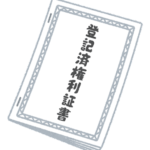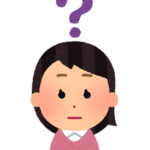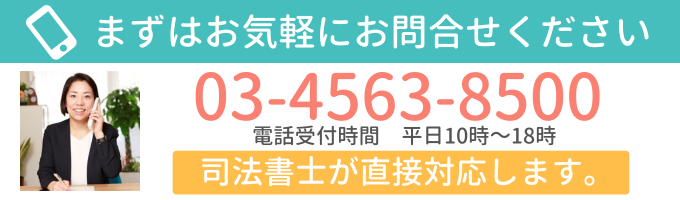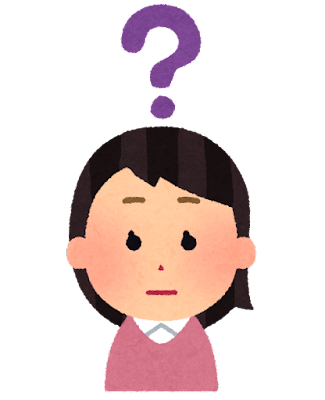
コロナ渦が落ち着きを見せ、ようやく人と交流できる生活が戻ってきてあらためて痛感したこと。
それは、司法書士の認知度低!ということです。
ここ1年と数か月、司法書士に用がある人のみと接していたためうっかり忘れていました。。
これは司法書士業界が広報下手だけではなく、きっと発信していない私にも責任がある。
ということで、解説記事とは異なる、食べ物ネタばかりのブログとも異なる、エッセー形式で少しずつ司法書士やその業務について発信していこうかと思います。
トップバッターのお題は、一番よく聞かれる「司法書士と行政書士のちがい」について。
試験の難易度が・・とまずは声を大にしていいたいところですが、いやそこではありません。
大枠をいうと、司法書士の監督官庁は「法務省」、行政書士の監督官庁は「総務省」ということ。
司法書士の主な仕事は、法務局への不動産登記・法人登記の申請代理、裁判所に提出する申立書や訴状等の書類作成代理です。
具体的なおしごとでいうと、相続登記(不動産の名義変更)、会社設立、裁判所への相続放棄など。さらに、所定の研修を受け試験に合格した認定司法書士は、訴額が140万以下のとなる簡易裁判所管轄の民事事件のみ、弁護士のように代理権が付与されています。
一方、行政書士の主な仕事は、官公署(各省庁、都道府県庁、市区役所、町・村役場、警察書等)、への提出する書類作成や許認可等に関する手続きの代理です。イメージしやすい例でいうと、運送業や飲食業の営業認可などでしょうか。
ではなぜ、世の多くの人が見わけがつかないことになっているのか?
行政書士は役所への許認可業務等のほかに、法で「その他権利義務又は事実証明に関する書類作成」も業務として定められおり、行政書士さんはこの規定をよりどころとして「民事法務」といって、遺言や遺産分割協議書作成、会社設立の定款作成、契約書作成、内容証明の作成などの法まわりの業務を取り扱っています。
一方、司法書士は専門である相続登記をはじめとする不動産登記や会社登記に関する業務と関連して、遺言や遺産分割協議書作成、会社設立の定款作成、契約書作成にも対応しています。内容証明の作成は簡裁代理業務にかかる業務です。
この結果、異なる士業なのに、同じような領域を扱っている状態が出来上がっているいるわけです。
あらためて、司法書士は「登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家」なのですが、さらに近年、簡易裁判所の訴訟代理等を行う業務、成年後見業務、財産管理業務や民事信託などが加わり、業務や役割が多様化した結果、「司法書士(何をしている人?もやっ。)」になっているかと。この「もやっ」が、少しづつ晴れていくように、日ごろの業務のこぼれ話をしながら情報発信していこうと思う次第です。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
まずは、司法書士に非常にあるある、司法書士を名乗って3分後に「行政書士さんって・・・」といわれる日がなくなることを願って。
-

-
相続の相談は弁護士・司法書士・税理士・行政書士・信託銀行…どの専門家にすればよい?
続きを見る
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日