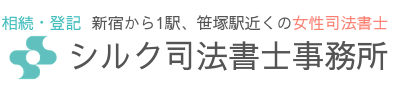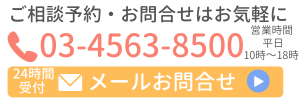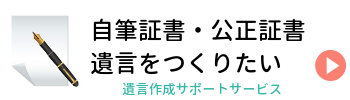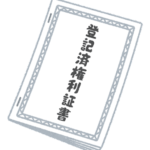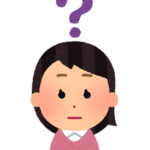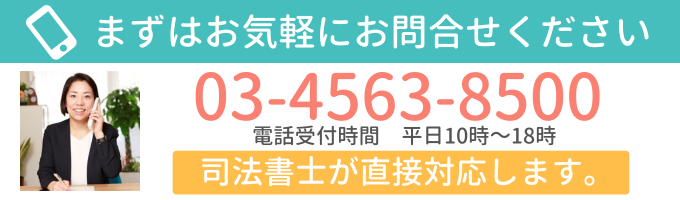「もめない相続なんてあるんですか!?」
時おり、弁護士さんとお話をしていると出る言葉です。
もめている相続のお仕事はできない司法書士の答えは「いっぱいありますよ!」なのですが、弁護士さんはもめている相続のお仕事ばかりされているので、このような会話が成立してしまうわけです。
司法書士がとある相続人のかわりに交渉等を行うことは非弁行為となるため、もめている相続は扱えません。依頼をうけるときにも「もめていませんよね?」(実際にはこんなダイレクトな言葉は使いませんが)という点はかなり注意深く確認します。
それでもやはり、受けた案件がもめてしまうことはあります。
司法書士がよく遭遇する、いわゆる「ふつうの家庭」でもめる相続といえば「亡き親と同居をしていた子である依頼者が、自宅を全て相続したい」というケースです。
もちろん依頼者がこうした主張をするのは、亡き親から生前に託されていた、介護をしていた、生活費や入院費などの出費をしていた、家の修繕費や固定資産税を払っているという相当の理由があるからです。
相当な理由があるから、自分が相続するのは当然であり、兄弟姉妹も納得いっていると信じています。そのため司法書士の依頼前の「もめていないか確認」も「大丈夫です!」とお答えされます。
ところが蓋をあけてみると、同じ子なのに相続分がないのは不公平、わずかな預貯金や現金だけでは納得いかないというほかの兄弟姉妹の反発が。
依頼者としては青天の霹靂なのですが、住宅取得や教育でお金が必要なタイミングであったり、妻子の意向やアドバイスによるものであったり、実はずっと愛情や金銭面の不公平を感じていた等、反発する兄弟にも相応の事情があったりします。
相続登記などは、たいてい代表相続人から依頼を頂き相続人調査(戸籍収集)からはじめるので、依頼前に全員に司法書士から確認をとるというのは難しく、進めてみないとわからないことがあるのです。
同居をしていた依頼者は、自宅を相続できないと生活基盤を失うことになるので譲れません。こうして話し合いが並行し、いわゆる「もめている状況」というのができてしまいます。
このようなケースの多くは、最終的には「法定相続分での相続」がベースとなり、不動産に対して預貯金や現金が足りない場合は「自宅を売ってお金をわける」ということを検討せざるをえません。関係がこじれもはや当事者同士の話し合いが難しくなった場合は、依頼者には弁護士さんを紹介します。
不動産の額以上の預貯金があればよいのですが、都市部、特に東京23区ではなかなか難しいところ。亡くなる前に数千万の預貯金が残っているのは、一般の人が思うところの「お金持ち」です。「お金持ちではなくても相続でもめる」「遺産の額は関係ない」という言葉の意味がちょっと理解できますでしょうか。
相続人が、おじ・おばとおい・めいというようなケースでは、「長子が当然相続する」「よその家に嫁いだ人は相続に関係ない」というような昔ながらの考えと、「与えられた権利は主張・行使する(もらえるものはもらう)」というような、世代間の価値観の違いによりもめることもあります。
冒頭の弁護士と司法書士のように、兄弟同士・相続人同士でも立場や状況によってまったく見えている世界が異なるということがあるものです。ここを理解できるかが、円満な遺産相続を導く大事なポイントではないででしょうか。
司法書士としては、残される相続人のために、しっかりしているうちに(認知症等になる前)に遺言書を残す習慣がもっともっと根付くことを祈るばかりです。
最新記事 by 司法書士 長谷川絹子 (全て見る)
- 令和5年度夏季休業日のお知らせ - 2023年7月20日
- Vol.9 司法書士の私が40代でも遺言書を残している理由 - 2022年2月24日
- Vol.8 司法書士と抵当権抹消 - 2022年2月1日